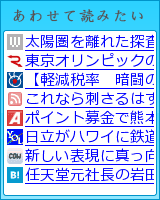◆価格で勝負するリスク
起業で陥りやすい罠に「価格で勝負してしまう」というものがあります。
低価格で勝負すると、最初はうまく行っても、のちのち痛い目を見る確率が高いです。
なぜなら、「起業してすぐのような小さな会社では、価格競争において大企業に勝てない」からです。
経済学の言葉に「規模の経済性(スケールメリット)」というものがあります。
これは「生産規模が大きくなるほど、生産物ひとつ当たりのコストが下がる」ことを意味しています。
職人が時間をかけてひとつひとつ手作りする製品と、作業者が分担して一気に大量に作る製品。
どちらが安く作れるかは言うまでもありません。
つまり、価格に関して言えば、「分業して一気に効率的に作ることができる」大企業には勝てないのです。
先駆者メリットを狙った起業で新たな需要に食いついても、価格以外の付加価値がなければ、のちのち大企業に食われてしまいます。
ですから以下のことを見極めることが重要です。
1、「売り」が安さだけになっていないか?
2、埋もれていた新たな市場なのか、「大企業がまだ手を付けていないだけ」の市場なのか?
3、競合と明確に差別化できるだけの付加価値を持てるか?
逆に、以上の3つがきちんと考えぬかれた市場での起業であれば、高い確率で成功するといえるでしょう。
◆価格競争から脱した例
成功した例として、「でんかのヤマグチ」のケースが挙げられます。
もとは東京都町田の老舗電器店。
3万人の顧客を抱え、経営は順風満帆でした。
ところが1996年、大型量販店が「規模の経済性」をタテに出店攻勢をかけてきて状況が一変し、経営が一気にピンチに陥ります。
ここで社長はどうしたか。
なんと、既存顧客へのきめ細かいサービスを生かすため、既存顧客を4割まで絞込んだのです。
この方策により、安さを求める客=量販店、高くても細かいサービスを求める客=「でんかのヤマグチ」という差別化に成功します。
ものは高いが、価格以上のサービスを受けられる。
機械があまり得意でない女性や高齢者を中心に、強烈な支持を得ることができました。
結果として、社員一人当たりの粗利が1000万円以上、粗利率37.8%という高収益起業へ生まれ変わったのです。
業界内の構造改革の流れを読み、競合との棲み分けを考える。価格競争に足を踏み入れない。
起業という果敢な挑戦をするからこそ、マーケティングの基本を抑えることが重要なのですね。
この記事を読んだかたは以下の記事も見ています
No related posts.